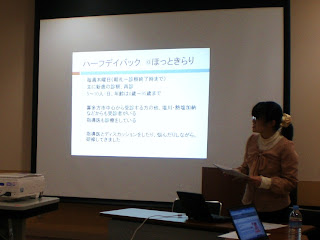来年度から、大学教員職を退き、いわきに腰を据えて診療・教育活動を行なうことになったわたくし。
家具らしきものはすでに運び出し、すっかり小物だけになった教員公舎で、洗濯かごをひっくり返した仮設テーブルとキャンプ用品の器でウィスキ―を傾けながら、明日の最後の授業(医学部4年生の講義)の準備をしている。
フランスの誇りを伝えきったアメル先生のように、家庭医の魅力と家庭医療に関わる者としての誇りを伝えきり、これから臨床実習を始める彼らが、新しい医療人として高い志を持って旅立てるように努めたい。
ご興味がおありの方ならご聴講(というよりご参加)も大歓迎!
<内容>
医療入門1「プライマリ・ケアと地域医療」特別講義
家庭医が地域で実践しているプライマリ・ケアについて、より多く
実際の患者さんのストーリーを追いながら、臨床推論スキルや包括
ぜひこの機会に“家庭医の醍醐味”を体験してみませんか?
「患者さんが教えてくれた家庭医の役割」
家庭医が地域で実践しているプライマリ・ケアについて、より多く
実際の患者さんのストーリーを追いながら、臨床推論スキルや包括
ぜひこの機会に“家庭医の醍醐味”を体験してみませんか?
「患者さんが教えてくれた家庭医の役割」
日時:平成25年3月7日(木) 8:40~11:50 (1・2時限)
場所:福島医大 6号館 第4講義室
対象:医学生、看護学生、研修医その他
家庭医療に興味のある方ならどなたでも大歓迎です!
場所:福島医大 6号館 第4講義室
対象:医学生、看護学生、研修医その他
家庭医療に興味のある方ならどなたでも大歓迎です!